体育祭が2日間、というのは珍しいでしょうか。そうでもないでしょうか。私にとっては初めての観戦経験でした。
甥っ子とはいえ2日間も観てるのは正直かったるいかな、と思ってましたが、とんでもなかった!
体育祭の概要
高校生になった甥っ子の初めての体育祭。先週の連休に開催されました。
ここは工業高校。建築科や都市工学科、進学コースなど全部で9つの科・コースがあります。体育祭はこの9つの科・コースの戦いになります。
普通は紅組・白組ですよね。私の母校の経験で言えば、定時制もありましたから、これに加えて青組。3つのチームの戦いです。
チームが9つとなると、時間がかかる。
たとえば応援合戦は9チームがやります。1チーム4分という時間制限で、掛け算すると36分。次のチームの準備などもありますから、+αで1時間はかかるでしょうか。
綱引き、騎馬戦といった競技は、トーナメント制のような形ではあるものの、やはり試合数は多くならざるを得ません。
こういった事情で、普通よりは時間がかかる=>2日間になる、ということなのでしょう。でも、2日間というのを感じさせなかった、熱い時間が繰り広げられました。
応援合戦が熱かった
1クラス40人☓9科☓3学年=1,080人。1つの科は120人となります。たったの120人なのですが、応援合戦の際、応援団以外の生徒が陣取るスタンドから聞こえてくる応援の声は、すさまじく力強いのです。
科には「染織デザイン科」があり、女子の割合が高い。貧弱になるのかと思いきや、声の質は違えども力強さは男子に負けてません(結局、応援合戦は染織デザイン科が優勝しました)。
そして私が心動かされたのは、どのチームも応援が揃っていることでした。演舞、応援の声援など。これだけ揃っているということは相当な練習をしたであろうことは疑う余地がありません。
この体育祭に向けて、各チームが真剣に、短い時間に集中して作りあげる、その情熱をみていると、「あー、おれはなんて怠惰なつまらない日々を送っているのか」と情けなくなりました。「オレも負けてられないぞ、オレはおれの仕事を一生懸命やらなければ」、いまさらながらそんな想いをいだきました。
組み体操はなかったけど
話題になっている組み体操は、ここではありませんでした。でも、集団行動がありました。
高校生の集団行動ですから、かの有名な日本体育大学のそれと比較はできません。しかも、高所から撮影する映像があるわけでもなく、同じ地面からの目線なので、どれだけ彼らの行動が素敵なのか、わかりません。が、それでも、規律はとれている行動であることはわかり、ユーモアもあり、素敵な発表を楽しめました。
ケガがどうのこうの、と話題になった組み体操ですが、そのかわりに集団行動という選択肢もあるのでは。
スウェーデンリレー
スウェーデンリレーをご存知でしょうか。第1走者が100m,以下200m,300m,400mと、徐々に一人あたりの長さが長くなるリレーです。
私の母校でも開催されており、非常に盛り上がる種目です。でも卒業後、これに遭遇したことはなく、今回ひさしぶりの観戦でした。
私の甥っ子が出場し、しかもそのチームが1位だったということもあるのですが、いやー、興奮しました。距離に合わせたペースを、それぞれの走者は考えなければなりません。たとえば400mを走る走者はその距離に合わせたペースでなければならないのです(ゆっくりスタートします)が、そういう事情を知らないでレースをみていると「なんでのったり走ってるんだよ」と思ったりします。逆に、ペースを考えないで加速する走者を見て「そうそう、それくらい走らないと前に追いつかない」と思うわけです。
でも、ペースを考えないで飛ばした走者を、ペースを守っていた走者が追い越していく。こういう駆け引きが、このレースにはあります。普通のリレーに比べてめまぐるしく様子が変わるのが、この種目の魅力。それを全開で楽しめました。
紅旗・白旗
他にも触れたいことがたくさんあるのですが、最も印象に残り、面白いと感じたのを最後にご紹介。
この体育祭では、紅旗と白旗が競技運営の肝です。どういうことかというと。
「紅上げて、白上げて、赤下げないで・・・」というあのゲーム(なんという名称ですかね)を思い出してみてください。あのゲームのように、1人が紅旗と白旗を一本ずつ手に持ちます。柄が眺めの旗です。これを上下させることで、いろいろな種目の制御をします。
たとえば。
徒競走
走者がスタート前に、ラインをはみ出ることなく位置について準備ができた。すると、それをチェックする係員は、それまで挙げていた紅旗をゆっくり下ろし、白旗を挙げます。それを確認した、演台に立つ競技全体の管理者は笛を吹きながら、これまた紅旗をゆっくり下ろし白旗を挙げます。そして白旗が全部挙がり切るあたりでスターターがピストルを鳴らし、スタートです。わかりにくいのですが、後の方の紅白の旗の上げ下げが「位置について、よういどん」になっています。
同じく徒競走やリレーなどでは、トラックのコーナー部分を、ラインの外側を規定どおりに走り抜けたかをチェックし、それを審判員に見せるため、白旗を掲げます。
アイアンマン
アイアンマンというのは、40kgの布袋を両手で頭上に長く掲げる、その時間を競うのですが、競技開始の準備ができたかどうかのチェックや、おろしてしまった競技者を紅旗で示すなどがわかりやすいです。
騎馬戦
騎馬戦は一対一の対戦ですが、残った騎馬の数を示すのに、やはり白旗を活用し、競技の管理者、観戦者にわかりやすく示します。
実際に観ていないとわかりにくいのですが、紅白旗の活用は非常に興味深かったです。
惰性の日々を送る、サラリーパーソン。かたや、懸命に力強く成長する高校生たち。彼ら彼女らの熱い姿に、私自身を鼓舞させる必要を感じた、熱い2日間でした。
【追記】
別の学校で聞いた話でもありますが、最近の体育祭は、体育祭当日だけではなく、本番までの練習の態度なども採点の対象になっています。ここでもそうでした。
なので、体育祭開会前の得点板にすでに得点が表示されてました。




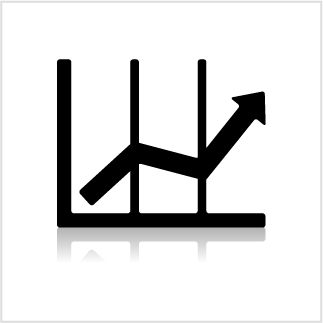

コメント